商談や会議の際、取引先や顧客、または従業員に渡す手土産代は、状況によって「接待交際費」「会議費」「広告宣伝費」「福利厚生費」などの勘定科目で仕訳します。
お土産代は基本的に経費として計上できますが、注意すべき点もあります。
経費として認められないケースがあるほか、勘定科目はいくつかパターンがあるため、担当者が正しく理解することが重要です。
本記事では、お土産代の勘定科目・仕訳の具体例や、経費として認められないケースを中心に、会計処理を行う際のポイントについて解説していきます。
お土産代の仕訳に使う勘定科目と経費にできるケース
お土産代の会計処理に用いる勘定科目は、主に以下の4つになります。
- 「接待交際費」:顧客や取引先などに渡すための手土産代を支払ったとき
- 「会議費」:会議や商談の場で渡す飲み物などの手土産代を支払ったとき
- 「広告宣伝費」:不特定多数の対象に対しての手土産代を支払ったとき
- 「福利厚生費」:自社の従業員に対して手土産代を支払ったとき
では、それぞれの勘定科目と経費にできるケースについてみていきましょう。
接待交際費
顧客や取引先など、事業に関係する方々にお土産を渡す場合、「接待交際費」として計上することができます。
ちなみに「接待交際費」とは、以下のように定義されています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
(引用元:国税庁HP「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」©国税庁)
「接待交際費」に該当するケース
接待交際費の範囲は幅広く、例えば以下のようなケースがあります。
- 取引先への訪問時に渡すための手土産の購入
- お歳暮やお中元、謝礼品
- 取引先が主催するイベントへの弁当の差し入れ
- 来客用のお茶菓子の提供
「接待交際費」に該当しないケース
ただし、以下のケースは、交際費に該当しないので注意しましょう。
- 専ら従業員の慰安を目的とした運動会、演芸会、旅行などのために使う費用
- 1人あたり10,000円以下の飲食費
- カレンダーや手ぬぐいなどの社名入りの物品を贈与する費用
- 会議でのお茶菓子、お弁当などの飲食物を提供する費用
- 出版物または放送番組の編集にかかわる座談会や取材に必要な費用
これらは、別の勘定科目が適当なケースです。
会議費
会議費とは、取引先との打ち合わせや商談に際しての社内や会議を行う場所での昼食の程度を超えない飲食代のことをいいます。
顧客や取引先との会議や商談にあわせて、飲み物やお茶菓子をお土産として提供する場合、この費用を「会議費」として計上することができます。
ただし、1人あたりの金額が10,000円を超える場合は、「接待交際費」として処理する必要がありますので注意しましょう。
「会議費」として書類ために必要な情報
「会議費」として処理するためには以下の情報を記載した書類の保存が必要になります。
- 飲食が行われた日付
- 参加した取引先や仕入れ先の名称や氏名、それらの関係性
- 会議や商談に参加した人数
広告宣伝費
「広告宣伝費」とは、不特定多数を対象に宣伝効果を期待して支出する費用のことです。
例えば、
- 自社商品のサンプルや試供品
- 自社名入りのカレンダーや手帳などの記念品
が該当します。
自社にとって宣伝効果のある品物をお土産とする場合は、「広告宣伝費」の勘定科目を使って経費にすることができます。
福利厚生費
「福利厚生費」とは、役員や従業員の福利厚生を目的として支出する費用のことです。給与や交際費とは異なり、従業員全員に平等に支出される費用が対象となります。
顧客や取引先ではなく、従業員にお土産を渡す場合には、その費用を「福利厚生費」として処理できるケースがあります。
例えば、従業員全員を対象とした飲み物やお茶菓子などの手土産は「福利厚生費」に該当します。
ただし、福利厚生費の適用には「平等であるか?」がポイントになります。
特定の従業員にのみ、お土産を渡した場合、その費用は「福利厚生費」として処理することができない点に注意してください。
経費として認められないお土産代
お土産代が経費として認められないケースには、主に次のような例があります。
- 家族や友人などプライベートの手土産
- 特定の従業員へのお土産
- 換金性の高い手土産
事業に関係のない家族や友人へのお土産は、個人的な購入としてみなされるため、経費にすることはできません。
また、特定の従業員にのみ渡すお土産も、経費として認められない点に注意が必要です。
さらに、図書券のような換金性の高い金券類も、経費として処理できない可能性があります。
ケース別:お土産代の仕訳の具体例
お土産代を仕訳するときは、状況によって使われる勘定科目が異なります。
本記事では、いくつかのケースに分けて仕訳を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
取引先への手土産として菓子折を購入した場合
取引先へお土産として5,000円の菓子折を現金で購入した場合は、「接待交際費」として以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 交際費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
取引先との会議にお茶菓子を提供した場合
取引先との会議で1,000円のお茶菓子を現金で購入した場合は、「会議費」として以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
取引先や顧客に対して配布を目的に社名入りのカレンダーを作成した場合
取引先や顧客に対して、配布を目的に100,000円の費用をかけて社名入りのカレンダーを作成し、支払いは請求書払いで行った場合は、広告宣伝費として以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 100,000円 | 未払金 | 100,000円 |
出張先で従業員へのお土産を購入した場合
出張の際に、全従業員分へのお土産として11,000円分を現金で購入した場合は、福利厚生費として以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 11,000円 | 現金 | 11,000円 |
お土産代を会計処理する場合の注意点
お土産代を会計処理する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
特に注意しておきたいことを紹介しますので、確認しておきましょう。
あまりに高額なお土産代は経費として認められない可能性がある
お土産代は社会通念上、経費として認められる範囲内にする必要があります。
あまりに高額な手土産代は、経費として認められない可能性があるため、注意しましょう。
どのくらいから「あまりに高額」かと言われると、明確な金額の規定はありませんが、事業規模に見合わない高額な手土産代は避けるのが無難です。
また、図書券などの換金性の高い物や金券などは、換金目的と判断される可能性があります。そのため、手土産として使用することは避けた方が良いでしょう。
法人は「交際費」の損金算入に制限がある
お土産代を「接待交際費」として処理する場合、会計上は問題ありませんが、税務上では損金算入に限度額がある点に注意が必要です。
接待交際費は、実は、全額損金不算入が原則とされています。

法人の種類や区分に応じて、一部の接待交際費について損金算入が認められる措置が設けられています。
| 法人の規模 | 損金不算入額 |
|---|---|
| 資本金または出資金の額が1億円以下 | 以下のいずれかの金額 1.交際費等のうち、飲食費の50%を超える額 2.交際費等のうち、800万円(事業年度の月数が1年未満のときは月で割る)を超える額 |
| 資本金または出資金の額が1億円超100億円以下 | 交際費等のうち、飲食費の50%を超える額 |
| 資本金の額または出資金の額が100億円超 | 交際費等の額の全額 |
(引用元:国税庁HP「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」©国税庁)
飲食以外の費用を交際費として損金算入できるのは、資本金1億円以下の企業が対象です。
ただし、資本金1億円未満の企業であっても、損金算入できる交際費には800万円の上限が設けられています。
そのため、交際費を無制限に損金算入できるわけではない点に注意しましょう。
プライベートと混同しないように注意する
法人だけでなく、個人事業主も取引先や顧客など事業に関係する方へ渡すお土産代を経費として計上することが可能です。
ただし、事業とは関係のないプライベートな付き合いのある人へのお土産は、経費として認められません。そのため、プライベートのお土産を混同して処理しないよう、注意しましょう。
また、個人事業主であっても従業員を雇っている場合、福利厚生費としてお土産を計上することが可能です。ただし、同一生計の親族は従業員には該当しないため、この点も押さえておきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回はお土産代の勘定科目、仕訳の具体例、注意点などについてみていきました。
お土産代については、状況によって適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
また、各勘定科目を使用する際にも注意点がありました。
特に交際費については税務上の損金限度額もあるので、注意が必要です。
複雑な部分もありますが、本記事を参考に、お土産代の仕訳や会計処理に役立てていただければ幸いです。
この記事がバックオフィスで働く皆さんのお役に立てば幸いです。
そして、今後も税務・会計に役立つ記事を発信していきますので、またお越しいただければ嬉しいです。
それでは、また!

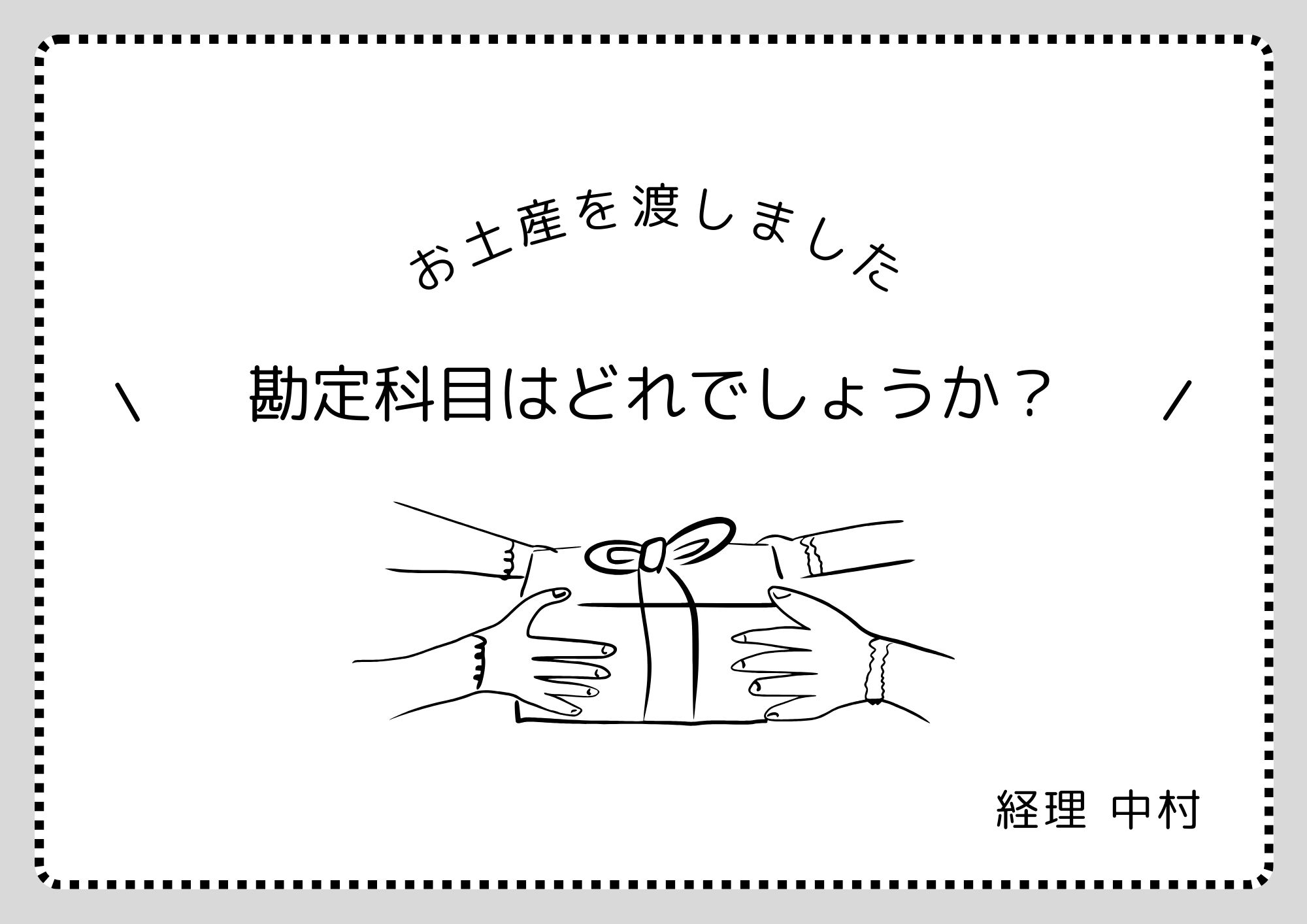








コメント